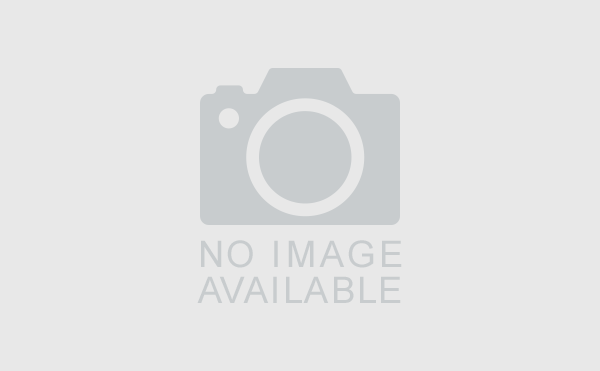“効率”より“大切なこと”を ― 若い先生が今こそ育てたい『働く力』

「もっと効率的に」「ムダを減らして」。
学校現場でも、そんな言葉をよく耳にするようになりました。
確かに、働き方改革の流れの中で、効率化は避けて通れません。
しかし、その波の中で、“働く力”そのものが弱くなってはいないか?
わたしは最近、そんなことを感じています。
若い先生の中には、「要領よくこなす」ことに長けた人も増えました。
けれども、子どもや同僚と丁寧に関わる粘り強さや、難しい状況でも諦めずに踏みとどまる力は、効率化だけでは育ちにくい力です。
それは、数字で測れない“人としての筋力”のようなものです。
この記事では、心理学の視点から「働く力とは何か」を掘り下げ、短期的な成果よりも、長く続けるための“本質的な強さ”を考えます。
効率化の先にある“しなやかな仕事力”――今こそ、そこに目を向けてみませんか。
1.Point:効率よりも、“人としての働く力”を育てよう
効率的に仕事をこなすことは、もちろん大切です。
しかし、教師という仕事には、効率だけでは測れない“働く力”があります。
それは「子どもの表情を見逃さない目」「困っている同僚に声をかける勇気」「小さな努力を続ける粘り強さ」など、データ化できない“人としての筋力”です。
この力を育てるのは、マニュアルではなく、日々の試行錯誤の積み重ねです。
2.Reason:効率の先にある“働く力”とは何か
最近、若い先生たちの中に「仕事を早く終わらせることが良いことだ」と感じる風潮があります。
もちろん、限られた時間で成果を出すスキルは必要です。
けれども、教育という仕事は「効率化」と「関係性」のあいだで、いつも揺れています。
ある若手の先生が、こんなことを話してくれました。
「子どもの小さな変化をしっかり見ようとするとどうしても時間がかかってすまうんです」
この言葉に、わたしは大きくうなずきました。
教師の仕事の本質は、人を理解し、支え、育てること。
だからこそ、「遠回りに見える関わり」が、最終的には子どもの力を引き出します。
効率的なやり方を学ぶのは悪いことではありません。
しかし、「目の前の一人にどれだけ心を向けられるか」――その姿勢を忘れた瞬間、教師としての成長は止まります。
心理学で言えば、こうした粘り強さは「グリット(やり抜く力)」や「レジリエンス(回復力)」と呼ばれます。
これらは一朝一夕に身につくものではなく、経験の中で少しずつ鍛えられていく。
効率的な方法よりも、失敗して、立ち止まりながら「自分なりの働き方」を探る時間が、人を育てるのです。
3.Example:現場で“働く力”を育ててきた先生たち
●子どもを信じて待つ勇気を持てた先生
ある若手の男性教師は、クラスのトラブルに直面したとき、すぐに介入する癖がありました。
「早く収めること」が正しいと思っていたのです。
けれどもある日、先輩から言われました。
「子どもが自分で気づくまで待つのも、教師の仕事だよ」と。
その後、彼はすぐに答えを与える代わりに、子どもの言葉を引き出すよう心がけました。
最初は時間がかかり、非効率に見えました。
けれども、ある女子児童が泣きながら「先生、話せてよかった」と言った瞬間、彼は気づいたそうです。
「あぁ、急ぐよりも、信じて待つ方が大事なんだ」と。
この“待つ力”こそが、まさに教師としての働く力です。
●同僚とのすれ違いから学んだ「聴く力」
別の女性教師は、学年会議での意見の衝突に悩んでいました。
「正しいことを言っているはずなのに、伝わらない」。
それでも一度、思い切って「どうしてそう思われるんですか?」と尋ねてみたそうです。
その瞬間、空気が変わりました。相手の先生も本音を語り始めたのです。
効率的に議論を終わらせようとすれば、対立は避けられます。
しかし、“聴く勇気”と“時間をかける覚悟”があってこそ、関係は深まります。
彼女はその後、「人間関係も、時間をかけて磨く仕事なんですね」と笑いました。
人との関わりの中で生まれるこうした学びが、働く力を豊かにしていきます。
●「一歩引く」ことを覚えた教師
わたしが見てきた中で印象的なのは、真面目すぎる先生ほど“頑張りすぎてしまう”こと。
すべてを完璧にしようとして、力尽きてしまうケースもあります。
でも、ある40代の先生はこう語りました。
「若い頃は全部抱え込んでいました。でも、あるとき“他の人に任せてもいい”と気づいたんです」。
彼女は若い先生にこう伝えています。
「一歩引くことも“働く力”の一部なんですよ」と。
無理に背負い続けることではなく、自分の限界を知り、助けを求める力。
それもまた、教師として成熟するための大切なスキルなのです。
4.Point:効率化は目的ではなく、手段である
効率化は悪ではありません。
むしろ、効率化によって生まれた“ゆとり”をどう使うかが大事です。
本を読む、同僚と語る、子どもをじっと見守る――
そうした時間が、教師の“働く力”を深めます。
わたしは若い先生たちにこう伝えています。
「早く終わらせることより、“納得して終えること”を目指してほしい」と。
丁寧に考え、悩み、失敗しながらも、自分の中で“仕事の意味”を見つける。
それが、どんな時代にも通用する“働く力”です。
まとめ:効率の時代に、人の温度を取り戻そう
働き方改革が進む今こそ、私たちは“働く意味”を問い直すときです。
短時間で成果を出す力だけでなく、「人と関わりながら働く力」を磨く。
それが、教育の世界で生きるための本当のスキルではないでしょうか。
もし今、「自分は要領が悪い」「仕事が遅い」と感じている先生がいたら、その“丁寧さ”こそが、あなたの持ち味です。
- 効率よりも、心をこめる。
- 急ぐよりも、つながる。
その積み重ねが、いつかあなたの教室に温かい風を吹かせるはずです。