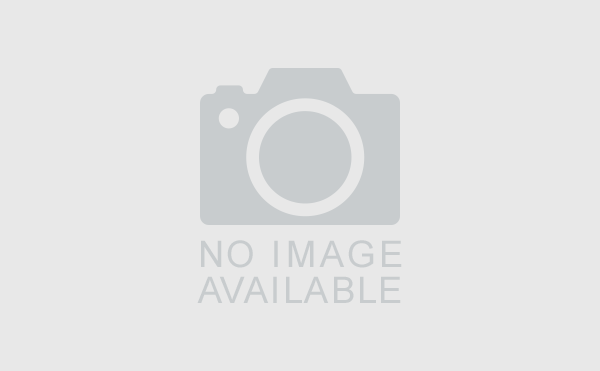課題未提出を「成長のチャンス」に変える教師のマインドセット

- 課題を出してもやってこない子を見ると、つい「なんでやらないの?」とイライラしてしまう
- 同じ子が何度も未提出を繰り返すと、「もうこの子は諦めよう」という気持ちになる
- 課題をやってこない子への対応で、学級全体の雰囲気が悪くなることがある
- 「きちんとやってくる子が損をする」という思いで、公平性に悩んでしまう
わたしも20年間の教師生活で、そんな場面を数え切れないほど経験してきました。
課題未提出の子を前にして、怒ったり、あきらめたり、時には見て見ぬふりをしてしまったことも正直あります。
でも、大学で教育心理学を学び、多くの先生方のカウンセリングに携わる中で、ひとつの大切なことに気づいたのです。
課題をやってこない子は、わたしたち教師に「何かを教えてくれる存在」だということを。
今日は、課題未提出を単なる問題行動として捉えるのではなく、その子なりの学びのペースや方法を理解し、教師自身の指導観を豊かにしていく視点についてお話しします。
きっと、課題をやってこない子への見方が変わり、あなた自身の教師としての幅が広がるはずです。
その子が教えてくれるものに、耳を傾けてみませんか?
1.Point:課題未提出は子どもからの「大切なメッセージ」
課題をやってこない子を前にしたとき、わたしたちはつい「問題のある子」「困った子」というレッテルを貼ってしまいがちです。
でも、長い教師経験を通して、わたしは確信を持って言えることがあります。
課題未提出は、その子からの大切なメッセージなのです。
「今の学び方では、ぼくには合わない」
「家では集中できる環境がない」
「もっと違う方法で理解したい」
「実は、わからないところがたくさんある」
そんな声にならない声を、課題未提出という形で伝えているのかもしれません。
わたしたち教師が、この「メッセージ」を受け取り、その子なりの学びのペースや方法を尊重することで、教師自身の指導観も豊かになっていきます。
課題未提出を成長のチャンスに変える。
それが、今日お伝えしたい核心です。
2.Reason:なぜ課題未提出を「問題」として捉えてしまうのか
そもそも、なぜわたしたちは課題未提出を「問題」として捉えてしまうのでしょうか。
一つには、学校教育が「均質性」を重視してきた歴史があります。
同じ課題を、同じペースで、同じ方法で取り組むことが「当たり前」とされてきました。
この枠組みの中では、課題をやってこない子は「逸脱者」となってしまいます。
また、わたしたち教師自身が「きちんと課題を出すこと」に責任感を持ちすぎているのかもしれません。
課題未提出の子がいると、まるで自分の指導力が問われているような気持ちになる。そんな経験、あなたもありませんか?
わたしも若い頃は、課題を出すことが教師の仕事だと思い込んでいました。
でも、ある日、課題をやってこない生徒に「先生、俺、家で勉強するより、友達と話しながら学ぶ方がよくわかるんだ」と言われたことがありました。
その時、思わず『ほんとうかぁ』とおもったのですが、その一方はっとしたのです。
わたしは「課題を出すこと」にばかり注目して、「その子がどう学びたいか」を見ていなかったことに。
さらに、現代の子どもたちを取り巻く環境も複雑化しています。
共働き家庭の増加、習い事の多様化、SNSやゲームといったデジタル環境。
従来の「家で静かに宿題をする」という前提が成り立ちにくくなっているのです。
こうした背景を理解せずに、昔ながらの「課題は必ずやるもの」という固定観念にとらわれていると、子どもたちの多様な学びのニーズを見落としてしまいます。
課題未提出を「問題」として捉える前に、まずはその背景にあるものに目を向ける。
それが、教師としての成長の第一歩なのです。
3.Example:課題未提出から学んだ具体的な事例と実践
事例1:中学2年生のタケシくんが教えてくれたこと
中学2年生のタケシくんは、ほぼ毎日課題を忘れてくる子でした。
先生は最初、「なぜやってこないの?」と叱っていたそうですたが、ある日、放課後に話をしてみると驚くべきことがわかりました。
タケシくんは、読書感想文の宿題について「本を読むのは好きだけど、感想を書くのが苦手。
でも、友達に本の内容を話すのは得意です」と言うのです。
そこで、「じゃあ、今度は書く代わりに、クラスのみんなに本を紹介してもらおうか」と提案したそうです。
結果、タケシくんは生き生きと本を紹介し、クラスメイトも興味深そうに聞いていました。
その後、タケシくんは「書く」課題も少しずつ取り組むようになったのです。
課題の形式を変えることで、その子の学びの扉が開いたのでした。
事例2:家庭環境に配慮した課題設計の工夫
コーチングでお会いした小学校の先生から聞いた話です。
その先生のクラスには、祖母と二人暮らしで、夜遅くまでコンビニでアルバイトをしている母親を待っている子がいました。
その子は算数の課題をほとんどやってきませんでした。
先生は家庭訪問で状況を把握し、「朝の10分間」を活用した課題システムを作りました。
登校後すぐに、前日の復習を短時間で行う仕組みです。
また、その子が得意な「人に教える」という特性を活かし、課題で困っている友達をサポートする役割も与えました。
すると、その子は算数への取り組みが劇的に変わりました。
「家でできないなら、学校でできる時間を作ろう」
そんな発想の転換が、子どもの学習意欲を引き出したのです。
事例3:課題の質を見直すきっかけ
高校の先生の話です。
英語の課題を頻繁に忘れるユミさんがいました。
ある日、「なぜ英語の課題だけやってこないの?」と聞くと、「先生の課題は答えを写すだけで、英語が上手になった感じがしないんです」という率直な答えが返ってきました。
その言葉に、愕然としたそうです。
確かに、その先生が出していた課題は、文法問題集の決まった範囲をやってくるだけのものでした。
ユミさんの指摘を受けて、課題を「自分の興味のある英語の歌詞を調べて、意味を考えてくる」といった、より創造的なものに変えました。
すると、ユミさんだけでなく、クラス全体の英語への関心が高まったのです。
課題未提出の子が、わたしの指導方法を見直すきっかけを与えてくれたのでした。
実践のポイント:課題未提出を成長につなげる3つの視点
これらの経験から、大切にしたいと思っている3つの視点をお伝えします。
まず「好奇心の視点」です。
なぜこの子は課題をやってこないのか、批判的になる前に純粋に好奇心を持って接してみてください。
その子なりの理由や事情があるはずです。
次に「柔軟性の視点」です。
課題の形式や方法を変えることで、その子の学びが活性化する可能性があります。
一つの方法にこだわらず、多様なアプローチを試してみましょう。
最後に「成長の視点」です。
課題未提出の子への対応を通して、自分自身の指導観や教師としての幅を広げる機会と捉えてみてください。
子どもたちは、わたしたちに多くのことを教えてくれる存在なのです。
4.Point:課題未提出を通して、教師も子どもも共に成長する
課題をやってこない子への対応は、確かに難しいものです。
でも、その難しさの中にこそ、教師としての真の成長があるのではないでしょうか。
大切なのは、課題未提出を「失敗」や「問題」として捉えるのではなく、その子からの「学びのメッセージ」として受け取ることです。
そして、そのメッセージに応えようとする中で、わたしたち自身の指導観も豊かになっていきます。
課題の形式を変える、取り組む時間や場所を工夫する、その子の得意な方法を見つける。
そうした試行錯誤の過程で、一人ひとりの子どもの学びに寄り添う力が育っていくのです。
もちろん、すべてが思い通りにいくわけではありません。
わたし自身、失敗を重ねながら今に至っています。
でも、課題未提出の子と向き合う中で学んだことは、確実にわたしを豊かな教師にしてくれました。
今、課題をやってこない子を前にして悩んでいるあなた。
その子は、きっとあなたに大切なことを教えてくれようとしています。
ぜひ、その声に耳を傾けてみてください。
まとめ:子どもの「学びのメッセージ」を受け取る教師へ
課題未提出は、子どもからの大切なメッセージです。
そのメッセージを受け取り、その子なりの学びのペースや方法を尊重することで、教師自身も成長していきます。
明日から、課題をやってこない子を見る目を少し変えてみませんか?
「なぜやらないの?」ではなく、「この子は何を教えてくれようとしているのだろう?」という好奇心を持って接してみてください。
きっと、新しい発見があるはずです。そして、その発見が、あなたをより豊かな教師へと導いてくれるでしょう。