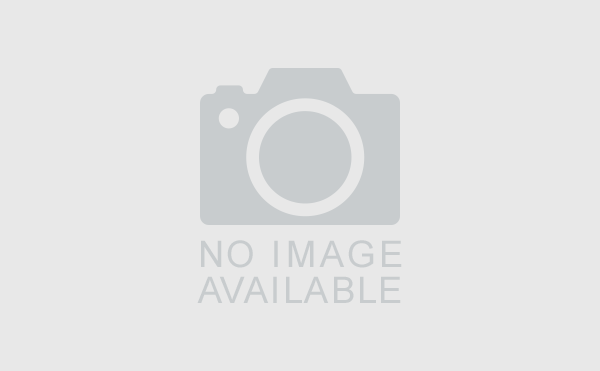「働き方改革」の時代に“とことん働く”意味を考える

「働きすぎ」は悪いこと。そんな空気が、教育現場にも少しずつ広がっています。
もちろん、健康を守り、長く続けるための「働き方改革」は大切です。
けれども、若い先生たちが「頑張りすぎないように」と言われ続ける中で、本来の「仕事に夢中になる喜び」まで失ってはいないでしょうか。
わたしは、これまで多くの先生方のキャリアを見てきました。
その中で、教師として伸び続けている人に共通しているのは、若い頃に「とことんやった経験」を持っているということです。
それは失敗や苦しみを伴っていても、後に自信や洞察へと変わっていきます。
この記事では、今の時代だからこそ問い直したい「仕事に夢中になることの価値」について考えていきます。
それは決して“働きすぎ”を肯定する話ではありません。
むしろ、教師として長く生きるための“熱中のバランス”を探る試みです。
一緒に、このテーマをじっくり味わってみませんか。
1.Point:今の時代だからこそ、“夢中になる時間”が必要だ
「働き方改革」が叫ばれる今、効率やバランスを重んじる風潮は大切です。
しかし、人生のある時期には“時間を忘れるほど夢中になる体験”が必要だと、わたしは思います。
それは単なる「長時間労働」とはまったく違います。
心から打ち込んだ時間は、あとになって深い洞察と確かな自信に変わります。
教師としての基礎体力や判断力、そして「仕事を通して生きる力」は、この“とことんやった経験”から育まれていくのです。
2.Reason:なぜ“とことん働く”時期が人を成長させるのか
若い時期に仕事へ没頭することには、心理学的にも明確な意味があります。
デシとライアンの自己決定理論では、人が健全に成長するためには「自律性・有能感・関係性」の三つの欲求が満たされることが重要だとされます。
若い教師が教室で試行錯誤を重ねるとき、これらの欲求が強く刺激されます。
つまり「自分でやりたい」「できるようになりたい」「誰かとつながりたい」という人間の根源的な動きが働いているのです。
また、心理学者チクセントミハイが提唱した“フロー体験”という概念も示唆的です。
人が心から打ち込んでいるとき、時間の感覚を忘れ、疲労を感じにくくなります。
この経験の積み重ねが、内発的動機づけを強め、「もっと学びたい」「次はこうしてみよう」といった自発的成長を生み出します。
とことん働く時期とは、実はこの“フロー状態”を繰り返し経験する時期でもあるのです。
もちろん、行き過ぎれば「燃え尽き」につながります。
しかし、燃え尽きの根底にあるのは、たいてい「孤立」と「無力感」です。
誰かに支えられながら挑戦できる環境があれば、熱中は消耗ではなく“エネルギーの循環”に変わります。
つまり、夢中になれる時期をどう支えるかが、組織としての課題なのです。
3.Example:若い頃の“全力”が、その後を支える ― ある先生の物語
以前、30代の女性の先生が来られました。
彼女は若い頃、部活動の顧問として朝も夜も学校にいました。
生徒のために全力を尽くし、休日も練習や遠征。
今思えば“働きすぎ”だったと苦笑いしていましたが、「でも、あのときに培った“本気で向き合う姿勢”が、今の自分の核なんです」と話してくれました。
今では家庭との両立を大切にしながら、若手の指導にも熱心です。
「当時の自分には無駄が多かった。でも、あの時期がなかったら、今の“余裕”も“優しさ”も生まれなかった」と語っていました。
まさに、“とことんやった時間”が“しなやかに働ける今”を支えているのです。
わたし自身も、若い頃はがむしゃらでした。
教材研究に没頭し、夜遅くまで教室で準備と一人リハーサル。
授業や生徒指導がうまくいかず、涙をこらえたこともあります。
でも、その一つ一つの苦しさが、今の講義やコーチング、カウンセリングの深みにつながっています。
誰かのために必死に動いた時間は、必ず自分の血肉になるのです。
研究的にも、このような“没入体験”は「自己効力感 self-efficacy」を高めることがわかっています。
一度「自分はやればできる」と感じた人は、その後も挑戦を続けやすくなります。
だからこそ、若手時代に「全力で取り組む体験」は、その後のキャリアを支える心理的基盤になるのです。
4.Point:働き方改革の本質は、“働き方の選び方”を学ぶこと
わたしは「働き方改革」と「夢中になること」は対立しないと思っています。
むしろ、「自分のエネルギーをどこにどう使うか」を考える力こそ、真の働き方改革です。
若い時期にとことん働くことは、その“配分感覚”を身につける貴重な機会なのです。
すべてを効率化し、リスクを避けるだけでは、人は伸びません。
失敗して、泣いて、笑って、心から動いた経験が「自分の仕事を愛する力」につながります。
それが後の持続可能な働き方を支える“心の筋肉”になります。
とことん働くことは、単なる努力ではなく、未来への投資なのです。
まとめ:熱中の季節を、誇りにして生きよう
若いうちにとことん働くことは、決して古い価値観ではありません。
それは「心が動く方向に全力を注ぐ」という、人生の自然な流れです。
ただし、その熱中を支える人とのつながりと、少しの自己客観が必要です。
もし今、あなたが「忙しすぎる」「報われない」と感じているなら、その時間の中に、きっとあなたを成長させている何かがあるはずです。
いつか必ず、その“夢中の時間”が未来のあなたを支えてくれます。
どうか、自分の歩みを信じてください。
働き方改革の時代にこそ、「とことん働いた自分」を誇りにできる教師でいてほしいと思います。