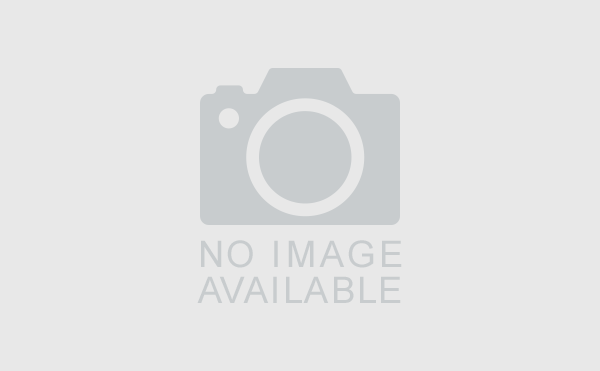感情コントロール”を育てる学級づくり ― 日常の関わりが「情動の筋トレ」になる

子どもたちの中には、ちょっとしたことで怒ったり、泣いたり、感情の波が激しい子がいます。
「どうしてこんなに感情を抑えられないのだろう」と、戸惑う先生も少なくありません。
けれど、感情をコントロールする力は、生まれつき備わっているわけではなく、人との関わりの中で少しずつ育っていく“筋力”のようなものです。
わたしも、トラブルを繰り返す子どもたちに悩みながら、その子の「怒り」や「涙」の奥にある不安や混乱に気づかされたことがありました。
今では心理学や脳科学の知見からも、日常のちょっとした関わりが“情動のトレーニング”になることが明らかになっています。
この記事では、学級の中でできる「感情コントロールを育てる関わり方」を、心理学的な視点と実践のヒントから紹介します。
子どもたちが自分の気持ちと上手に付き合い、クラス全体が穏やかに過ごせるようになる手立てを、一緒に考えてみましょう。
1.Point:感情は「教え込む」ものではなく「育てる」もの
感情のコントロールは、叱って教えられるものではありません。
それは、日々の生活の中で少しずつ鍛えられていく“情動の筋トレ”のようなものです。
教師の穏やかな言葉かけや、安心できる教室の雰囲気こそが、子どもたちにとってのトレーニングの場になります。
「感情を抑えさせる」のではなく、「感情を扱えるように育てる」こと。
これが、現場の先生ができる最も大切なアプローチです。
2.Reason:感情をコントロールできない背景には“未熟さ”と“安心の欠如”がある
感情を爆発させたり、些細なことで泣いたりする子どもを見ると、「我慢が足りない」「落ち着きがない」と感じてしまうかもしれません。
けれど、心理学的に見れば、それは「悪い性格」ではなく、「発達の途上」なのです。
人間の脳では、感情を生み出す「扁桃体」がまず反応し、それを制御する「前頭前野」があとから働くようにできています。
つまり、感情の制御には時間がかかるのです。
子どもほどこの制御システムが未熟であり、特にストレスが高い状況では、前頭前野の働きが鈍り、感情が一気にあふれ出します。
さらに、感情のコントロールには「安心感」も不可欠です。
愛着理論でも、子どもが安心できる関係性の中でこそ、自己抑制や他者理解が育つとされています。つまり、落ち着かない子ほど「安全な基地(セーフベース)」を求めているのです。
たとえば、授業中にふざけてしまう子や、友達に強く当たってしまう子。
その裏には、「注目してほしい」「自分を認めてほしい」という心のサインが隠れていることが多いのです。
行動だけを問題視すると、対立が深まりやすくなります。
しかし、感情の背景を見ようとするまなざしがあると、子どもの反応は少しずつ変わっていきます。
3.Example:感情コントロールを育てる3つの実践ステップ
わたしが現場の先生やコーチングの中で大切にしているのは、「環境・関係・言葉」の3つのアプローチです。
この三層を意識することで、子どもたちの情動コントロール力は確実に変わっていきます。
① 環境を整える ― 子どもが“落ち着ける場所”をつくる
感情が不安定な子どもにとって、「視覚的な刺激」や「雑多な空間」はストレスのもとになります。
たとえば、教室の掲示物が多すぎると注意が散漫になりやすく、緊張感が高まりやすいのです。
静かに休めるコーナーを設けたり、机の配置を工夫したりするだけでも、落ち着きやすさは格段に変わります。
また、「見通しを持てる環境」も大切です。
次に何をするのか、どんな流れになるのかが予測できると、子どもの安心感が増します。
スケジュールを黒板に書く、朝の会で1日の流れを確認するなど、日常の小さな工夫が効果的です。
② 関係を築く ― 「叱る前に寄り添う」姿勢を持つ
感情を爆発させる子どもには、「悪気がない」のに誤解されてしまう子も少なくありません。
そうした子どもに必要なのは、まず「受け止められる経験」です。
ある小学校の男の子(3年生)は、しょっちゅう怒って教室を飛び出していました。
先生がある日、追いかけるのをやめて廊下で静かに待っていると、数分後に彼が戻ってきて言いました。
「先生、今日は怒ってないんだね」
それ以来、その子は自分の気持ちを話すようになり、少しずつ行動が落ち着いていきました。
このように、「叱られない安心感」は感情調整の土台です。
行動の結果を正す前に、まず「気持ちをわかってくれた」と感じさせる。
それが、情動コントロールの第一歩になります。
③ 言葉を育てる ― 感情を“見える化”していく
感情をコントロールする力は、「自分の気持ちを言葉にできる力」と深く関係しています。
心理学ではこれを「感情のラベリング」と呼びます。
「悲しい」「怒っている」「イライラする」「寂しい」と言葉にできると、脳の扁桃体の興奮が鎮まることがわかっています。
学級の中でできる工夫としては、以下のようなものがあります。
・朝の会で「今の気持ち」を天気マークで表す
・けんかのあとに「どんな気持ちだった?」と問いかける
・絵本や詩を通して「登場人物の気持ち」を考える時間を持つ
これらは単なる活動ではなく、「情動の言語化練習」です。
最初はうまく言葉にできなくても、「わからない」も大切な一歩。
教師が「そう感じたんだね」と受け止めることで、子どもは自分の気持ちを“扱える”ようになっていきます。
4.Point:感情を「整える力」は、日常の中で磨かれる
感情コントロールの力は、特別な授業で身につくものではありません。
日々の生活や対話、失敗ややり直しの経験の中で育ちます。
教師が「どうしたらこの子が安心して話せるだろう」と考える姿勢そのものが、子どもにとっての“情動教育”になります。
感情を抑えるよりも、感じてもいい、でもその後どうするかを一緒に考える。
その繰り返しが、感情を「敵」ではなく「味方」に変えていきます。
子どもたちの中に小さな変化を見つけたら、ぜひその瞬間を大切にしてください。
「成長の芽」は、叱る場面ではなく、寄り添った日常の中に宿ります。
まとめ:感情を育てる学級づくりは「心のトレーニング」
気持ちのコントロールが難しい子どもに出会ったとき、私たちは「指導」よりも「伴走」を意識したいものです。
環境を整え、関係を築き、言葉を育てる。
その積み重ねこそが、情動の筋トレとなり、子どもたちの“心の安定感”を育てます。
「感情をコントロールする力」は、生きる力そのものです。
今日から、あなたのクラスの中でも、小さな“心の筋トレ”を始めてみませんか。
きっと、子どもたちだけでなく、先生自身の心も少しずつ整っていくはずです。