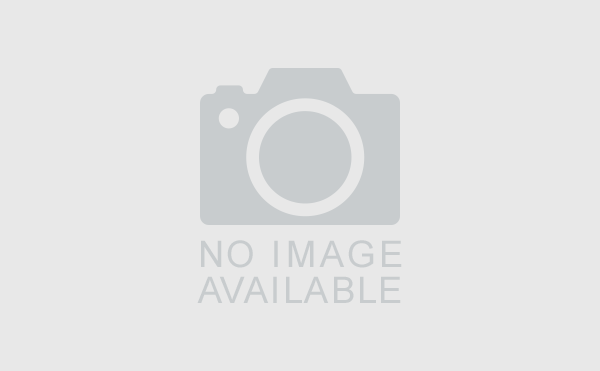ADHDの子との関わりで疲れ果てたときに立ち返る『3つの基本姿勢』

・何度注意しても同じことを繰り返すADHDの子に、つい声を荒げてしまった
・他の子にはうまくいく指導法が全く通用せず、自分の力不足を感じている
・クラス全体への配慮とその子への個別対応の板挟みで、毎日が綱渡り状態
・保護者対応でも悩み、「先生の指導が悪いのでは」と言われて心が折れそう
ADHDの子との関わりは、多くの先生が直面する大きな挑戦です。
特性を理解していても、日々の現実は想像以上に厳しく、気がつけば疲れ果てて自信を失ってしまうことも少なくありません。
わたしも学校現場で数多くのADHDの子と関わり、何度も壁にぶつかりました。
そして現在、大学で教員養成に携わりながら、多くの先生方の相談にのってきました。
そこで見えてきたのは、行き詰まったときにこそ立ち返るべき「基本姿勢」の大切さです。
今日お伝えするのは、テクニックや特別な指導法ではありません。
疲れ切ったあなたの心を少し軽くし、明日からまた子どもと向き合う力を取り戻すための、3つの基本的な考え方です。
完璧な指導を求めすぎて苦しんでいる先生、その子との関係に希望を見出せずにいる先生に、「それでいいんだ」と思えるヒントをお届けします。
先生方の毎日は、本当に尊いものだとわたしは思います。一緒に考えてみましょう。
1.Point:ADHDの子との関わりで行き詰まったら、3つの基本姿勢に立ち返ろう
ADHDの子との関わりで疲れ果てたとき、わたしたちが立ち返るべきは
「完璧を求めない姿勢」
「小さな変化を見つける視点」
「自分自身をいたわる心」の3つです。
多くの先生が、ADHDの子への指導がうまくいかないとき、「もっと良い方法があるはず」「自分の力が足りない」と自分を責めがちです。
しかし、長年の臨床経験から断言できるのは、完璧な対応など存在しないということ。
大切なのは、その子との関係性の中で「今、この瞬間にできること」を積み重ねることなのです。
この3つの基本姿勢は、テクニック以前の土台となるもの。
どんなに優れた指導法も、先生の心が疲れ切っていては効果を発揮しません。
まずは、あなた自身が穏やかな気持ちで子どもと向き合えるようになること。
それが、ADHDの子にとって最も必要な「安心できる環境」の第一歩となります。
2.Reason:なぜ基本姿勢が重要なのか〜ADHDの子と先生、双方の心理的背景
ADHDの子との関わりが困難になる背景には、子どもと先生、双方の心理的な悪循環があります。
ADHDの特性を持つ子どもは、脳の前頭前野の発達がゆっくりで、注意の制御や衝動のコントロールが苦手です。
しかし、それ以上に深刻なのは、日常的に「ダメ」「なぜできない」という否定的なフィードバックを受け続けることで生まれる二次的な問題です。
彼らは「また怒られた」「自分は悪い子だ」という思いを心に蓄積し、自己肯定感が著しく低下していきます。
一方、先生側にも大きなストレスがかかります。
他の子には効果的な指導が通用しない焦り、周囲からの視線への不安、「指導力不足」という自己評価の低下。
わたしがカウンセリングで関わった多くの先生が「この子のためを思ってやっているのに、なぜ伝わらないのか」と涙を流されました。
この悪循環を断ち切るには、まず先生自身が心理的に安定していることが不可欠です。
ストレスを抱えた状態では、どんなに良い方法を知っていても、それを冷静に実践することは困難になります。
臨床心理学では「治療者が安定していることが、クライエントの安定につながる」と考えます。
学校現場でも同様で、先生が穏やかでいることが、ADHDの子の情緒安定に直結するのです。
さらに重要なのは、ADHDの子の成長は「階段式」ではなく「上り坂と下り坂の繰り返し」だということです。
一度できるようになったことが、また元に戻ったように見えることがよくあります。
これは特性上当然のことなのですが、多くの先生が「後退した」と感じて落ち込まれます。
しかし、脳科学的に見れば、ADHDの子の脳は確実に発達しています。
ただし、その変化は非常に緩やかで、日々の関わりの中では見えにくいもの。
だからこそ、長期的な視点と、小さな変化を見つける「特別な眼差し」が必要になるのです。
3.Example:3つの基本姿勢の具体的な実践方法
(1) 完璧を求めない姿勢〜「60点で合格」の考え方
わたしがコーチングで関わった中学校のA先生の事例をお話しします。
クラスに強いADHD特性を持つ生徒がいて、授業中の立ち歩きや大きな声で話すことが頻繁でした。
A先生は毎日「静かにしなさい」「席に座りなさい」と注意し続け、次第に疲弊していきました。
「完璧な授業をしたい」「他の生徒に迷惑をかけさせたくない」という思いが強すぎて、その生徒の行動すべてを「問題」として捉えていたのです。
そこで、わたしは「今日は10分間座っていようと約束ができたら合格、本当に座れたら100点満点」という基準を提案しました。
最初は「それでは甘すぎる」と抵抗されましたが、実際に試してみると変化が起きました。
10分座れなかったとしても、まず「頑張ってみる」と約束できたことを認め、5分でも座っていられたら「お、〇〇君、5分間、頑張って座っていたね」と声をかけます。
そして「約束の10分間は長かったかな? じゃあ、今度は何分頑張ってみる?」と尋ねるのです。
10分という約束を守れなかったその子は、はじめは気まずそうな表情でしたが、明るい表情で「次は8分、いや、また10分頑張る」と言いました。
このように「60点で合格」という基準を設定すると、先生の心理的な負担を軽減するだけでなく、子どもが「成功体験」を積む機会を増やせます。
完璧を求めすぎると、先生と子どもの双方が疲弊する悪循環に陥りがちです。
そこで、わたしは「今日は10分間座わろうと約束が出来たら合格。本当に座れたら100点満点」という基準を提案しました。
最初は「それでは甘すぎる」と抵抗されましたが、実際に試してみると変化が起きました。
10分座れなくてもまず「頑張ってみる」と約束でき、それで5分でも頑張って座れたらまずそのことを認めてあげます。「お、〇〇君、5分間、頑張って座っていたね」。
そのうえで「約束の10分間は長かったかな?じゃあ今度は何分頑張ってみる?」と質問するのです。
10分という約束を守れなったその子は、はじめは気まずい表情だったのですが、明るい表情で「つぎは8分、いや、また10分頑張る」といったのです。
「60点で合格」の基準設定は、先生の心理的負担を軽減するだけでなく、子どもにとって「成功体験」を積む機会を増やします。
完璧を求めすぎると、双方が疲弊する悪循環に陥りがちです。
具体的には:
・授業中、5分間集中できたら「集中タイム、上手だった」と認める
・忘れ物が週3回から2回に減ったら「改善してるね」と伝える
・友達とトラブルになっても、自分から謝れたら「偉かったよ」と評価する
(2) 小さな変化を見つける視点〜「成長日記」のススメ
小学校のB先生は、ADHDの特性を持つ児童との関わりで「何も変わらない」と落ち込んでいました。
そこで始めたのが「成長日記」です。毎日、その子の小さな変化や良い面を1つだけメモする習慣でした。
最初の1週間:
・月曜:朝の挨拶、元気だった
・火曜:給食を完食
・水曜:友達が困ってるとき「大丈夫?」と声かけ
・木曜:宿題を半分やってきた
・金曜:掃除のとき、最後まで雑巾がけをしていた
「こんな小さなことを書いても意味があるのでしょうか」と最初は疑問視されていましたが、1ヶ月続けると、B先生の見方が変わりました。
「この子なりに頑張ってる部分がたくさんあったんですね」と目を潤ませながら話されたのを覚えています。
成長日記の効果は、先生の認知バイアスを修正することです。
人間は「問題行動」により注意が向きがちですが、意識的に「良い面」を探すことで、その子への見方が根本的に変わります。
(3) 自分自身をいたわる心〜セルフケアの重要性
高校のC先生は、ADHDの生徒指導に関わるあまり、休日も学校のことが頭から離れず、不眠に悩まされていました。
「その子のために」という思いは素晴らしいものでしたが、先生自身が疲弊しては元も子もありません。
わたしは「まず、あなた自身が元気でいることが、その子にとって一番大切です」と伝えました。
そして具体的なセルフケア方法を一緒に考えました:
・平日は19時以降、学校のことを考えない「スイッチオフタイム」を設ける
・週末は必ず半日、完全に自分の時間を作る
・同僚や管理職に、状況を共有して一人で抱え込まない
・月に1回、カウンセリングやコーチングを受けて気持ちを整理する
東日本大震災で家族を亡くしたわたし自身の経験からも言えるのは、支える人が支えられることの大切さです。
先生が心身ともに健康でいてこそ、子どもたちに安定した関わりを提供できるのです。
これらの基本姿勢は、決して「手抜き」や「諦め」ではありません。
むしろ、長期的な視点で子どもの成長を支えるための、戦略的なアプローチなのです。
4.Point:基本姿勢こそが最強の指導法〜明日からできる小さな一歩
ADHDの子との関わりで行き詰まったとき、新しいテクニックを探すよりも、まずは3つの基本姿勢に立ち返ることが重要です。
完璧を求めず、小さな変化を大切にし、自分自身をいたわる。
この土台があってこそ、どんな指導法も効果を発揮します。
わたしがカウンセリングで関わった先生方の多くが「特別なことをしなくても、気持ちが楽になっただけで子どもとの関係が改善した」と報告してくださいます。
これは偶然ではありません。
先生の心の状態が、子どもに直接伝わるからです。
明日からできる小さな一歩として、まずは「今日、その子の良かった点を1つ見つける」ことから始めてみてください。
それが見つからない日は、「今日も一日、その子と過ごせた」ということ自体を良しとしてみてください。
ADHDの子との関わりは、時に困難で疲れることもあります。
しかし、その分、小さな成長や変化に気づいたときの喜びは格別です。
完璧な先生である必要はありません。
その子と一緒に成長していく、そんな気持ちでいることが一番大切なのです。
まとめ
ADHDの子との関わりで疲れ果てたとき、立ち返るべきは
「完璧を求めない姿勢」
「小さな変化を見つける視点」
「自分自身をいたわる心」
の3つです。
新しいテクニックよりも、まずはこの基本姿勢を大切にしてください。
先生が穏やかでいることが、その子にとって最も安心できる環境となります。
今日から「60点で合格」「小さな成長日記」「セルフケアの時間」を意識してみてください。
わたしも、いつも道半ばです。一緒に学んでいけたら嬉しいです。