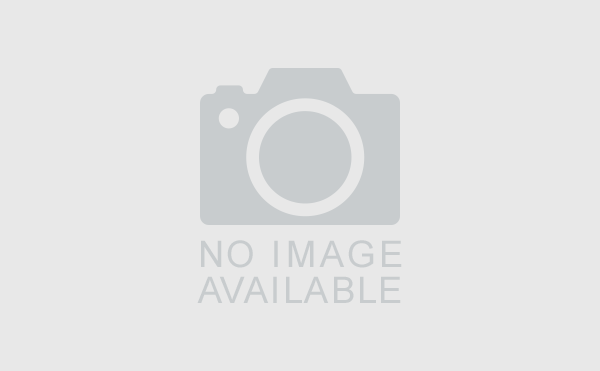“辞める”という選択肢が見えてきたとき、まず立ち止まって考えたい3つの視点

こんなふうに感じたことはありませんか?
- 仕事には向き合っているけれど、心がついていかない
- いつまでこの働き方を続けるのか、ふと不安になる
- 辞めたいと思ったものの、「辞めたあとどうなるのか」が怖い
わたしも長く学校現場にいて、そうした声をたくさん聞いてきました。
もしかしたら、あなたも今、そんな揺らぎの中にいるかもしれません。
教師を辞めるという選択は、人生の大きな岐路です。
収入の減少や再就職の不安、家族や周囲の目。
簡単に決められることではありません。
それでも、「辞めたい」と思ったときは、
あなたの中で“何かが変わり始めている”サインです。
今日は、「辞める・辞めない」をすぐに決める前に、
一度立ち止まって考えてほしい3つの視点を紹介します。
1. Point(導入):辞める前に、「過去・現在・未来」の3視点で整える
「教師を辞めたい」と思ったとき、大切なのは、“辞めるか続けるか”を即座に決めることではありません。
むしろ、その気持ちが生まれた背景にこそ、大切なヒントがあります。
教師という仕事は、専門性と情熱を求められる尊い仕事です。
しかし、それゆえに「やめる=逃げ」や「失敗」と感じてしまう人も少なくありません。
けれど、辞めたくなることは“変化の兆し”であり、あなたがこれまで大切にしてきたものと、今の現実の間に、ズレや違和感が生じている証でもあります。
そこで大切にしたいのが「過去・現在・未来」の3つの視点です。
この順番で自分を見つめ直すことで、表面的な感情ではなく、深い価値観に気づくことができます。
結果として、自分にとっての納得のいく選択が見えてくる。
それが、「辞める前に立ち止まって考えるべきこと」なのです。
2. Reason:なぜこの3つの視点が必要なのか?
教師を辞めることは、単なる「転職」ではありません。
それは、生活や人間関係、収入、社会的立場にいたるまで、大きな変化をもたらす決断です。
だからこそ、焦らず、急がず。
辞める・辞めないの二択にする前に、いま自分が立っている場所を確認する必要があります。
● なぜ「過去」が大切か?
自分がどんなことにやりがいを感じていたのか、どんな場面で「教師でよかった」と思えたのか。
それを思い出すことで、「今つらいのはなぜか」が、よりはっきりしてきます。
感情の奥にある「価値観」に気づく作業です。
● なぜ「現在」が必要か?
人は、自分でも気づかぬうちに、「こうあるべき」「教師なら我慢すべき」と自分を縛ってしまいます。
でも、心がしんどいまま働き続けるのは、自分にも、子どもにも、職場にもいい結果をもたらしません。
「苦しいのは、わたしが弱いからじゃない」
そう気づくことが、次の一歩を探す準備になります。
● なぜ「未来」を見つめるのか?
仕事のことだけを考えていると、どうしても“教師か、それ以外か”という極端な思考になりがちです。
でも、あなたが本当に望んでいるのは、「仕事」ではなく、「生き方」や「暮らし方」ではないでしょうか。
10年後の自分がどんな生活をしていたいのか。
子どもとの関係、パートナーとの時間、自分の趣味や体調……
それを描くことが、今の選択に軸をもたらしてくれます。
● 現実的な懸念:収入は確かに減る
多くの人が口をそろえて言います。
「辞めたら、収入はかなり下がる」と。
これは確かに現実です。
特に年齢が上がるほど、同等水準の給与を得られる仕事は限られます。
住宅ローンや子どもの進学費用があれば、なおさら慎重になります。
でも、それでも辞める人がいるのは、「お金では買えないもの」を取り戻したいからです。
その決断ができるかどうかは、「何を優先したいのか」という価値観の整理にかかっているのです。
3. Example(再構成):3つの視点で自分を見つめ直す方法
「辞めようかな」と思ったとき、すぐに動き出すよりも、一度“自分の本音”に触れる時間をつくることが、後悔しない選択につながります。
ここでは、「過去・現在・未来」の3つの視点に沿って、どのように考え、書き出してみるとよいかを、具体例とともに紹介します。
● 視点1:過去――「夢中になれた瞬間は、何だったか?」
“教師になった理由”を思い出すのではなく、「いつ、自分はこの仕事に喜びを感じていたか?」を掘り下げてみましょう。
たとえば、ある中学校の先生はこう振り返っていました。
「進路指導で、普段あまり話さない生徒が“先生と話せてよかった”って言ってくれたとき、自分はただ点数を上げる指導より、子どもの“気持ちの節目”に関わることにやりがいを感じていたんだと気づいたんです」
また、別の小学校の先生はこう話していました。
「行事の前ってクタクタになるんですけど、当日の子どもの表情や達成感を見ると、心が満たされた。自分は“つくりあげる”ことが好きだったんだと思います」
こうした記憶には、あなたが教師として何に価値を感じていたのか、どんな瞬間に「わたしはここにいていい」と感じていたのかが隠れています。
感情の奥には、あなたらしい“教育観”や“人との関わり方”が宿っています。
過去の喜びややりがいの中にある共通点を探してみてください。
● 視点2:現在――「何がつらくて、なぜそこまで消耗しているのか?」
「とにかくしんどい」「もう限界」という感覚は、往々にして“複数の小さな違和感”の積み重ねから生まれます。
ある高校の先生が語ったのは、次のようなことでした。
「誰かの顔色を見ながら話さないといけない空気が、ほんとうに疲れるんです。自分はもっと率直に議論したいタイプなのに、“出る杭にならないように”って自分を抑えている」
また、別の先生はこんなふうに話していました。
「“いい先生でいなきゃ”という自分に、もう疲れてしまったんです。授業が終わって職員室に戻ると、いつもどこか演じているような気持ちになる。自分を失っている感じがしました」
現在の苦しさには、“組織の文化”との相性や、“自分らしさ”との乖離が大きく影響していることがあります。
その違和感を「忙しいから」「管理職が嫌だから」と一言で片付けてしまわず、
「なぜそれが自分にとってつらいのか?」と内省してみると、
“本当に手放したいもの”と“守りたいもの”が見えてくることがあります。
● 視点3:未来――「どんなふうに暮らしていきたいか?」
辞める・辞めないを考えるとき、見落とされがちなのが、「どんな暮らしを望んでいるのか?」という問いです。
ある先生は、こんな未来像を描いていました。
「朝7時に家を出て、夜8時に帰る生活を30年続ける未来は想像できなかったんです。もっと家族とご飯を食べて、子どもと話して、自分の趣味の読書に時間を使いたいと思ったとき、教師という働き方は違うかもしれないと感じました」
また、別の先生はこんなことを言っていました。
「本当は、もっと自然の近くで暮らして、週3日くらい働くような生活をしてみたい。今は“忙しいことが正しい”みたいな感覚が染みついていて、自分のペースがわからなくなっていた気がします」
未来の暮らしを具体的に描いていくことで、あなたが「何を優先したいのか」「どこで妥協したくないのか」が明確になります。
収入、住まい、人間関係、時間の使い方、健康――。
どれも“人生をかたちづくる要素”です。
「どんなふうに働くか」は、「どんなふうに生きたいか」の延長にあるのです。
このように、「過去」「現在」「未来」を行き来しながら、自分の感情と価値観をつなぎなおす時間をとってみてください。
紙に書いてみる。誰かに話してみる。小さなことで構いません。
大切なのは、「辞めるか・続けるか」を決めることではなく、「どうありたいか」に向かって、自分を見つめることなのです。
4. Point:正解ではなく、「納得できる答え」を見つけるために
誰かにとっての“正しい選択”が、あなたにとっての正解とは限りません。
だからこそ、他人の声に振り回されず、自分自身の声に耳を澄ませる時間を持つことが何よりも大切です。
収入や再就職の不安、家族の反応――。
辞めるか迷っているとき、現実的な要素がたくさん頭をよぎるのは自然なことです。
でも、それだけで決めてしまうと、いつか「こんなはずじゃなかった」と振り返ることにもなりかねません。
自分の過去にあった情熱、今の苦しさの正体、そしてこれからどう生きていきたいか――。
この3つを整理することで、“本当に大切にしたいこと”が見えてきます。
それはあなたにしかわからない、「納得できる選択」を導いてくれるはずです。
まとめ:人生のハンドルを、もう一度自分の手に取り戻すために
教師という仕事は、人の人生に深く関わる責任の重い仕事です。
だからこそ、その道を離れるかどうかを決めるのは、簡単ではありません。
けれど、「辞めようか」と思った時点で、あなたの中で何かが変わり始めているのも事実です。
今日ご紹介した3つの視点――
「過去に何を大切にしてきたか」
「今、何に違和感を感じているのか」
「これから、どんな生き方を望んでいるか」
これらを静かに見つめ直すことで、
「教師か、それ以外か」という二者択一ではない選択肢が見えてくるかもしれません。
人生のハンドルは、他人に預けず、自分の手で握り直していいのです。
わたしも、いつもその問いを繰り返しながら生きています。
一緒に、自分らしい道を見つけていけたら嬉しいです。